このブログを読むとわかること
 ハリキリBOY
ハリキリBOYボクがSNSで見かけた「無言の帰宅」という言葉の議論を整理し、日本語が廃れていく寂しさと同時に変化していく必然についての思いを綴ったよ。
また、言葉と向き合ううえで大切な「謙虚さを持ち続ける姿勢」についても共有するね。
日常生活の小さな出来事から、人としてのあり方を見直すきっかけになれば嬉しいな・・・
はじめに
最近X(旧Twitter)で「無言の帰宅」という言葉がトレンドに上がり、大きな議論を呼びました。
本来は「遺体となって帰宅する」という報道用語であるにもかかわらず、多くの人が「黙って帰る」と解釈して祝福の言葉を送ってしまったのです。
この誤解から浮かび上がったのは、慣用句が世代によって通じなくなっている現状と、人が「自分の知識こそ正しい」と思い込む危うさでした。
この記事では、その二つの論点を掘り下げ、「謙虚に学び続けること」が幸福につながるという私の考えを整理します。
学べること
結論から言えば、「無言の帰宅」騒動は日本語の変化と人間の姿勢について学べる教材です。
まず言葉の面では、慣用句や婉曲表現が廃れつつある一方、新しいスラングや表現が次々と生まれている事実があります。これは言語が常に進化している証拠です。
次に姿勢の面では、重要なのは「知らないこと自体」ではなく「知らなかったときにどう振る舞うか」です。自分の無知を認め、素直に学ぶ人は成長しますが、「そんな言葉を使うな」と相手を攻撃する人は学びを閉ざしてしまいます。
この二つを踏まえると、言葉をめぐる議論は単なる知識の問題ではなく、「学び続ける態度」を映す鏡だとわかります。
注意点
ただし、ここで注意すべき点がいくつかあります。
一つ目は、言葉の衰退を嘆きすぎると「昔は良かった」と懐古に陥りがちなことです。言葉は常に変わるものなので、古い表現が消えていくのも自然な流れです。
二つ目は、知識を絶対視してしまう危険性です。「自分の知識が正しい」と思い込むと、異なる解釈や新しい言葉を排除してしまいます。
三つ目は、今回の件が「実際に亡くなられた方」を背景にしていることを忘れないことです。議論を楽しむあまり、故人や遺族への敬意を欠いてはいけません。
これらを意識することで、健全に言葉と向き合うことができます。
所感
私自身、この騒動をSNSで見かけたときに「無言の帰宅」の意味を知っていました。しかし同時に、多くの人が誤解してコメントしている様子を見て、言葉の知識が世代や経験によって大きく異なることを実感しました。
この経験から学んだのは、「自分が知っている言葉を他人も知っているはず」と思い込むのは危険だということです。
私が実践しているのは、定期的に辞書を開いて新しく加わった言葉や削除された言葉を眺める習慣です。広辞苑は改訂のたびに進化しており、そこには日本語の「消えていくもの」と「生まれるもの」の両方が詰まっています。
さらに、ライトノベルや西尾維新のような娯楽作品も含め、文学に触れることで普段の生活では出会えない語彙やリズムに触れることができます。こうした習慣が、言葉に対する謙虚さを育ててくれると感じています。
よくある質問
- Q: 「無言の帰宅」は違法な表現ですか?
→ 違法ではありません。ただし現代では通じにくく、誤解を招きやすい表現です。 - Q: 「無言で帰宅」とはどう違うのですか?
→ 「無言で帰宅」は「黙って帰る」日常表現。一方「無言の帰宅」は報道用語で「遺体として帰宅する」を指します。 - Q: 言葉が廃れるのは悪いことですか?
→ 必ずしも悪ではありません。言語は常に変化しており、新しい表現が定着する一方で古い表現が消えるのは自然な現象です。
まとめ
今回の議論から得られた要点を整理します。
- 「無言の帰宅」は日本語の婉曲表現であり、通じない世代が増えている。
- 日本語は廃れると同時に新しく生まれる、常に変化する存在である。
- 大事なのは「知らないこと」ではなく「学び続ける姿勢」である。
- 知識を絶対視せず、謙虚に受け止めることで幸福度が高まる。
- 西尾維新の作品のように、日本語の豊かさに触れられる本は学びの教材としても優秀である。
- わからない言葉に出会ったら、その場で辞書を引いて調べる習慣が大切である。
私は「美しい日本語が廃れるのは悲しい」と思う一方で、「自分が正しい」と思い込む姿勢こそが危ういと考えています。
これからも謙虚に学び続けることで、言葉との関わりも、人との関わりも、より豊かにできるのではないでしょうか。
最後に、この出来事は実際に亡くなられた方をきっかけに広がったものです。改めて故人のご冥福をお祈り申し上げます。
あなたは「廃れていく言葉」とどう向き合いますか?

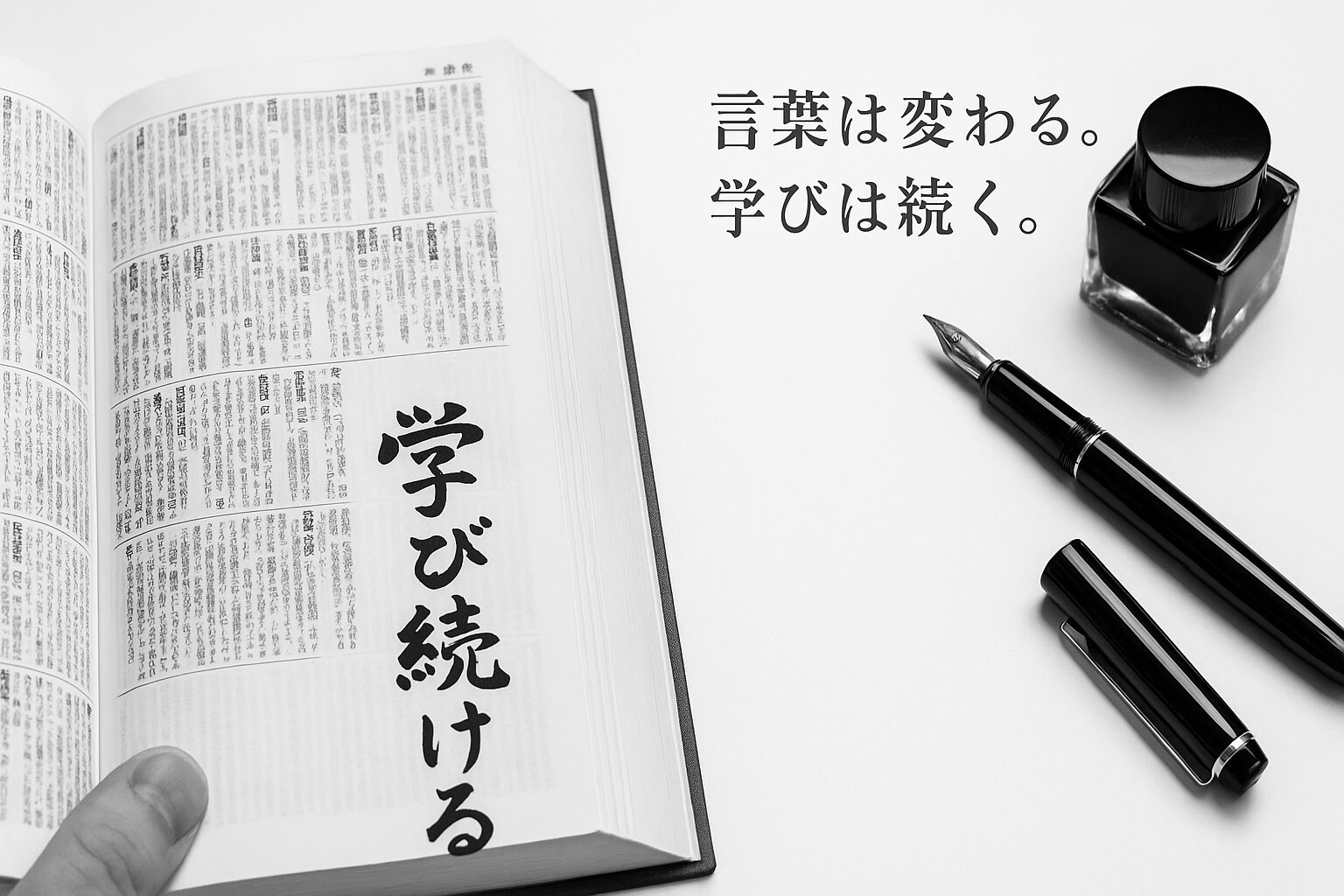
コメント