「犯罪者を納税者に」——心に刺さった一言
本書で最も印象に残ったのは、「犯罪者を納税者にする」という言葉でした。この一文に、本書の根底にある強いメッセージが込められているように感じました。
著者は、非行少年をただ「更生させる」のではなく、「納税者」として社会に参加できる存在へと導くためには、まずその子たちの“脳の仕組み”を理解し、適切な訓練と支援が必要だと説いています。これは決して理想論ではなく、社会全体で取り組むべき現実的な課題です。
思考と言語化ができないと人は暴力に走る
最近、「自分の思考を言語化できないから怒りに任せる人」が増えているように感じます。思い通りにいかないとすぐ怒鳴る、イライラをぶつける…。これは単に「癇癪持ち」なのではなく、感情のコントロールや自己理解がうまくできない特性を持った人たちなのかもしれない。本書を読んで、そのような視点を持つようになりました。
「自己責任論」が通用しない現実もある
日本社会は「自己責任」や「努力不足」といった言葉が好まれる傾向にあります。しかし、境界知能や知的障害のある人にとっては、どれだけ努力しても乗り越えられない“壁”があります。努力ではどうにもならない現実が存在するのです。
とりわけ重要なのは、そもそも善悪の区別すらつかないまま犯罪に至ってしまう人たちが存在するという事実です。相手が何を怒っているのかもわからず、言葉の意図も読めず、結果的に反省そのものができない。これは「開き直り」ではなく、認知機能の障害による“理解不能”という壁なのです。
ホワイトカラー社会と「境界知能」のギャップ
産業構造の変化も、本書の内容をより深く考えるきっかけになりました。農業や漁業、製造業が中心だった時代とは違い、現在は頭脳労働が中心の「ホワイトカラー社会」へと移行しています。パソコンやインターネットを使う業務が当たり前になり、それに伴って求められる知能の水準も上がったのではないかと感じています。
このような社会の変化の中で、境界知能の人々は仕事に就けず、非正規や無職になりやすく、やがて“社会のお荷物”と見なされ、周縁へと追いやられてしまう。そしてその一部は、最終的に犯罪へと手を染めてしまうかもしれません。
現場での実感と「見えない壁」
実は私自身、日常の中で「この人はもしかしたら認知の特性によって誤解されているのでは?」と思う場面に出会うことがあります。たとえば、職場で指示がうまく伝わらない人がいたとき、それを「サボっている」と捉えるのではなく、「処理の仕方が分からないのかもしれない」と想像することは大切だと感じるようになりました。
私たちはつい「普通ならこれくらい分かるだろう」と基準を押しつけがちですが、その“普通”が通じない背景には、目に見えない特性や困難が潜んでいる可能性があります。本書は、その視点を与えてくれました。
知識を「一般常識」にするには
本書に書かれているような内容は、教育関係者や福祉・医療の現場では広まりつつあります。しかし、それが「社会全体の常識」になるまでには、まだまだ時間がかかるように思います。知識として知っているだけでなく、日常の中で“想像する力”を持てるかどうかが、本当の意味での理解につながるはずです。
差別や偏見を減らすためにも、「学び続ける大人」が増えていってほしいと心から思います。私自身もその一人でありたいです。
まとめ:支援があれば、人は変われる
本書を通して、「非行」は結果であって原因ではないという視点を得ました。反省を求める前に、まずその行動の根底にある“認知”や“感情の未熟さ”を見つめ直す必要があるのです。
支援があれば、知的障害や境界知能のある人でも、立派な納税者として社会で役割を果たすことができます。それを実現するには、学校、医療、家庭、矯正施設、地域が一体となって支える体制が必要です。
今は理想論かもしれません。しかし、私は信じたい。「明日はもっと良くなる」と。

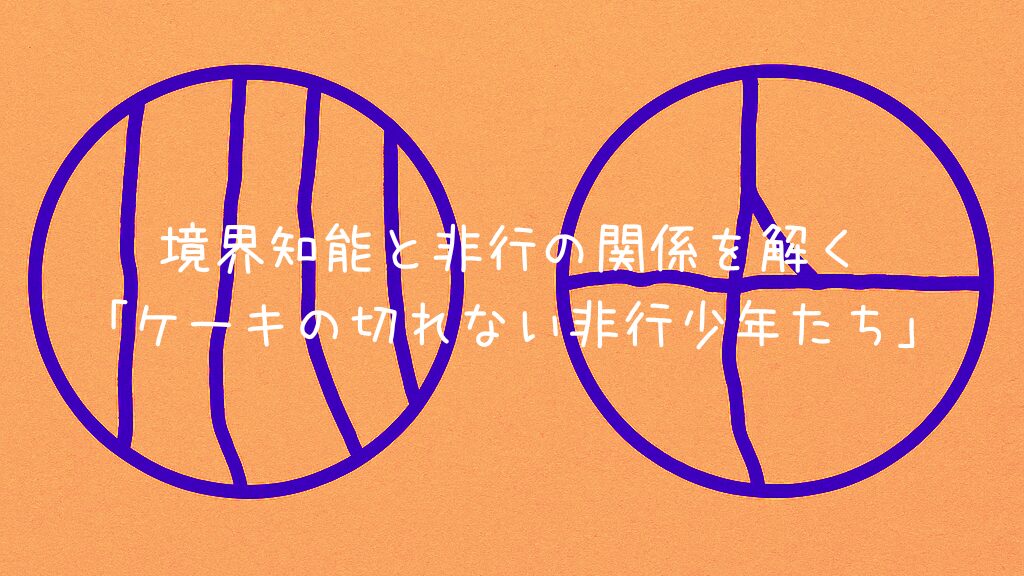
コメント